予防医療
大切な家族がいつまでも元気でいられるように

病気予防をしっかりしておくと、人間も同じですが、結果として費用も時間も節約できます。重症となれば何よりかわいい家族の一員を強く長く苦しめることになります。
また、「全部いっぺんに‥」というわけにはいきません。 狂犬病予防接種してから、混合ワクチンを接種するとしても1~2週間はあけないといけません。混合ワクチンをしてから狂犬病となるともっと期間をあけないといけません。 計画的に予防することが重要です。
えそら動物病院では、飼い主様とじっくり、じっくりお話をして、病気予防を計画的に行っています。
ワクチン接種

ワクチンの接種により、特定の感染症に対する免疫を獲得できます。免疫が備わっていれば、病気の発症や重症化を防ぎやすくなります。また、他の動物や人間への感染拡大防止という点でも、ワクチン接種は重要な役割を担います。大切な家族の一員であるペットたち、そして他の動物たちの命を守るためにも、定期的なワクチン接種を継続しましょう。
接種に適した混合ワクチンは、その子の体調や飼育環境により異なります。ワクチン接種のご要望は、まず当院にお問い合わせください。
ワクチンの種類
狂犬病ワクチン
狂犬病ウイルスはヒトを含むすべての哺乳類に感染します。かぜに似た症状からはじまり、興奮、麻痺、精神錯乱などの神経症状が現れ最終的には脳神経や全身の筋肉が麻痺を起こし呼吸ができなくなって死亡する病気です。世界中でも5万人もの人が毎年亡くなっているとても怖い病気です。発症するとほぼ100%助かりません。 日本ではここ数十年発生していない病気ですが、国内でも感染しないとは言い切れません。
ワンちゃんの飼い主様は、そのワンちゃんの登録と年に1回の予防接種を受けさせなければいけないと法律で決められています。毎年(4月~6月)しっかりと予防をしてワンちゃんを狂犬病から守ってあげましょう。
混合ワクチン

ワンちゃんの混合ワクチン
狂犬病ワクチンのように、接種が法律で義務付けられているワクチン以外にも、ワンちゃんの健康をサポートする任意の混合ワクチンがあります。混合ワクチンの接種により、命を脅かすさまざまな感染症からワンちゃんの健康を守ることができます。ワクチンの種類や接種に適したタイミングは、ワンちゃんの生活環境に応じて調整いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
6種の混合ワクチン
命に関わる怖い病気2つ(ジステンパー、パルボ)とワンちゃんのいわゆる『風邪』が予防できます。
家の周り(水辺以外)のお散歩や、家庭内生活、動物病院に行く、ドッグランに行く、しつけ教室に行く程度でしたら、6種混合がおすすめです。
予防できる病気
- 犬ジステンパー
- 犬パラインフルエンザ感染症
- アデノウイルスⅠ型感染症(犬伝染性肝炎)
- 犬パルボウイルス感染症
- アデノウイルスⅡ型感染症(犬伝染性咽頭気管炎)
- 犬コロナウイルス感染症
10種の混合ワクチン
他の動物と接触する機会が多い場合やキャンプ・猟などで山や水辺近くに行く、アウトドアで活動することの多い子、また、西日本の方へよく遠出をする子は10種をおすすめします。
予防できる病気
- 上記、6種ワクチンで予防できる病気
- レプトスピラ感染症4種

ネコちゃんの混合ワクチン
室内飼いのネコちゃんでも、感染症予防のためのワクチンは大切です。たとえ室内で過ごしていても、外部からの病原体の侵入は避けられません。逃げ出した際のリスクも考慮すると、ワクチン接種の重要性は高まります。治療が難しい感染症も存在するため、愛するネコちゃんの健康と安全のために、ワクチン接種をおすすめいたします。
3種の混合ワクチン
命に関わる怖い病気(猫汎白血球減少症)とネコちゃんのいわゆる『風邪』が予防できます。家の中の子でも感染する可能性のある病気です。
予防できる病気
- 猫伝染性腸炎
- 猫ウイルス性鼻気管炎
- 猫カリシウイルス感染症
4種の混合ワクチン
猫白血病ウイルス感染症は感染すると80%が3年以内に死亡します。外で他のネコちゃんと接触する可能性のある子はこちらがおすすめです。
予防できる病気
- 上記、3種ワクチンで予防できる病気
- 猫白血病ウイルス感染症
フィラリア予防
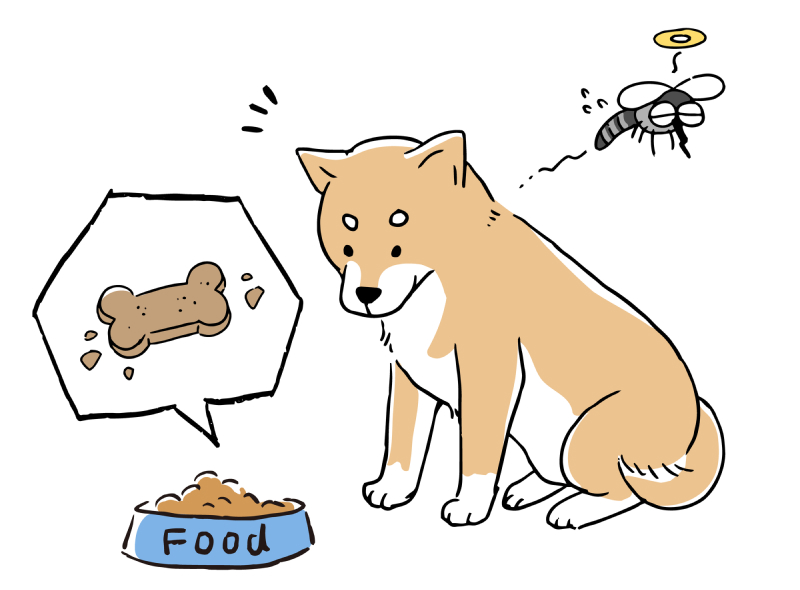
フィラリアは蚊を媒介し、体内に寄生虫が入り込む病気です。蚊に刺された際に寄生虫が体内に入り込み、心臓やその周辺の血管に寄生しながら成長し、さまざまな心臓のトラブルを引き起こす原因になります。
血液循環が悪くなり、最終的には死に至る怖い病気です。感染してしまうと治療するのが難しい、予防が非常に大事な病気です。
 主な症状
主な症状
- 元気がなくなる
- 呼吸が苦しそうになる
- お腹が膨れる
- 食欲が低下する
- 咳がでる
- 重症の場合、血尿やショックなど
予防について
フィラリア予防の期間は年によって変動しますが、冬でも生息しているため、当院では通年予防をしていただくことをおすすめしています。その理由は、暖冬などで条件が揃えば、冬場でも蚊は生息できるからです。また、蚊が多いという周辺環境にも考慮し、適切な予防が必要です。
気温や蚊の発生状況を考慮し、蚊が活動する期間および1か月後までの継続した予防が大切です。愛知県では、5月初旬~12月初旬までの約8か月間が、フィラリア予防の推奨期間とされています。専用の予防薬により、心臓に達する前に幼虫を排除する効果が期待できます。お薬の服用方法は、内服薬・チュアブル・スポットタイプなど、ワンちゃんの体調や飼育環境に合わせて選択可能です。
予防前は血液検査を行い、感染の有無を事前に確認する必要があります。
ネコちゃんのフィラリア予防

フィラリアはワンちゃんのみならず、ネコちゃんも感染する可能性があります。
血管内で死滅した蚊の幼虫が呼吸器に悪影響をもたらすことで、せきや喘息などの症状が現れやすくなり、呼吸困難や突然死などの重い症状を引き起こすこともあります。
たとえ完全室内飼いであっても、外部からの蚊の侵入は完璧には避けられません。ネコちゃんにおいても、フィラリア予防が強く推奨されています。
ノミ・ダニ予防

ノミやダニは屋内外を問わず、どこにでも存在しています。ワンちゃんやネコちゃんの体表に付着したまま、外部からノミやダニが入り込み、室内で大増殖する可能性も考えられます。ペットのみならず、人間にも皮膚トラブルを引き起こす原因になるため、適切な予防と駆除が欠かせません。
ノミ・ダニ予防の重要性
ノミやダニが寄生すると、ワンちゃんやネコちゃんの皮膚の炎症、かゆみ、貧血などの症状を引き起こします。また、サナダムシやバベシア症、Q熱やSFTS(重症熱性血小板減少症候群)など、さまざまな感染症のリスクが高まります。これらの感染症は人間も発症し、命の危機を伴う場合もあります。
ノミやダニの予防は、ペットと飼い主様の健康を考える上で必須です。
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)
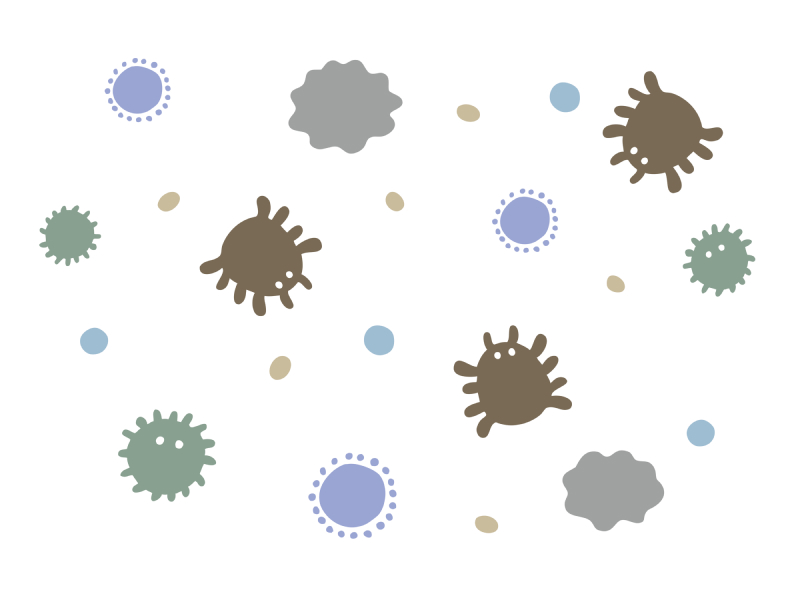
SFTSという中国由来の病気があり、重症熱性血小板減少症候群と言います。
この病気を引き起こす正体は、SFTSウイルスです。ウイルスを保有しているフタトゲチマダニ等のマダニに直接咬まれること、もしくは、マダニに咬まれて感染した動物の体液などにより感染します。感染患者の血液、体液との接触感染も報告されています。ウイルスの潜伏期間は6日~2週間程度といわれています。
主な症状は発熱とおう吐、下痢などが中心で、倦怠感、リンパ節のはれ、出血症状なども見られます。致死率は10~30%といわれています。
予防のポイント
野外でマダニ等に咬まれないようにすることが大切です。特にマダニの活動が盛んな春から秋にかけては注意が必要です。草むらややぶなど、マダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用し、肌の露出を少なくすることが大切です。
また、感染者の血液・体液・排泄物との直接的な接触も避けるようにしてください。野生動物に素手で触ることも避けてください。ペットの体調変化に注意し、健康状態不良時は動物病院に受診させてください。
ペットとの関係

犬や猫がお散歩中に草むらにいるマダニにかまれたり、そのマダニを人のいる環境に連れてきてしまうことがあります。 市販では確実な予防ができないものや安全性が確立していないものが販売されています。
確実な予防と安全のため、マダニ予防薬は動物病院で販売されているものをお勧めします。
エキノコックス

北海道!キタキツネの病気というイメージですが、愛知でも陽性犬が、2014年~2021年までに、阿久比、南知多、知多、半田、常滑で確認された感染症の一つで条虫です。キツネや犬などから排出された虫卵に汚染された水、食物、埃などを口から摂取した場合に感染します。
エキノコックスの潜伏期間は5年~15年と長く、発症後の死亡率は90%以上です。山やキャンプなどのアウトドア活動から帰宅後は、徹底した手洗いおよび泥や汚れをきちんと取り除きましょう。また、特に野犬やキツネなどの野生動物には、むやみに近づかないことが肝心です。また、エキノコックスの流行地域では、ワンちゃんの放し飼いはできるだけ避けるべきといえます。
人間が感染すると…
人間に感染した場合は、体内に発生した嚢胞は緩慢に増大し、周囲の臓器を圧迫します。多包虫病巣の拡大は極めてゆっくりで、肝臓の腫大、腹痛、黄疸、貧血、発熱や腹水貯留などの初期症状が現れるまで、成人では通常10年以上かかります。
放置すると約半年で腹水が貯留し、やがて死に至ります。
また、発症前や早期の無症状期でも、スクリーニング検査の超音波、CT、MRIの所見から検知される場合があります。
ワンちゃんが感染した場合は基本的に無症状なことが多く、駆虫薬を飲ませることで駆除できる病気ですが、人間に有効な治療薬はなく、外科的切除が唯一の根治的治療法です。
予防するには…
- 虫体を保持している・感染源になる可能性のある動物に接触しない
- 野山に出かけた後は、よく手を洗う
- 虫卵がついている可能性がある飲食物の摂取を避ける
- 沢や川の生水を飲む際は、よく煮沸してから飲むようにする
- 山菜や野菜、果物等はよく洗ってから食べる
- ワンちゃんが感染したネズミなどを食べる可能性があるため、放し飼いはしない
- ワンちゃんの散歩後や草むらで遊んだ際は、よく手足を洗ってあげる
